賃貸物件のオーナーやこれから賃貸経営を始めたい方にとって、「減価償却」は避けて通れない重要なテーマです。賢く資産を運用するためには、減価償却の基本や計算方法をしっかり理解しておく必要があります。
また、リフォームや修繕と減価償却の関係も見逃せません。この記事では、法定耐用年数や減価償却がもたらす家計・税金への影響、賃貸経営で押さえるべきポイントまで、基礎から実践まで分かりやすく解説します。
減価償却の基本 賃貸物件オーナーが知っておきたいポイント

賃貸物件を所有するうえで、「減価償却」は経営と税金の両面で大切な仕組みです。ここでは減価償却の基本を、賃貸オーナーの目線で分かりやすくご紹介します。
減価償却の仕組みと賃貸経営への影響
減価償却とは、建物や設備など長期間使う資産の購入費用を、数年に分けて経費として計上する会計上の方法です。賃貸経営では、築年数が経つごとに建物価値が下がるため、費用を一度に計上せず年ごとに分けて計上します。
この仕組みを活用することで、毎年の収入から経費を差し引くことができ、税金の負担を減らす効果が期待できます。賃貸収入が安定していても、減価償却を正しく行うかどうかで、手元に残る現金や資産の管理方法が大きく変わってきます。
減価償却費が家計や税金に与えるメリット
減価償却費をきちんと計上すると、課税対象となる所得が減り、税負担を軽くすることができます。たとえば、家賃収入から減価償却費を差し引いた額が所得となるため、同じ収入でも実際の税金は減る仕組みです。
また、減価償却を活用することで、長期的な資産計画やキャッシュフローの安定にもつながります。家計の管理や将来のリフォーム費用の備えとしても、減価償却を意識することは重要です。
賃貸物件で減価償却が必要な理由
賃貸物件は年数が経つにつれて建物が劣化し、その価値は徐々に減っていきます。減価償却をすることで、その劣化分を毎年の経費として計上し、利益とのバランスを取ることができます。
減価償却をしない場合、購入時の大きな費用をそのまま経費にできず、実際の利益が大きく見えてしまい、結果として税金が増えることもあります。資産の実態を反映するうえでも、減価償却は大切な会計手法です。
減価償却できる資産とできない資産の違い
賃貸物件経営では、すべての費用が減価償却の対象になるわけではありません。主に建物本体や付属設備が対象で、土地は価値が減らないため減価償却の対象外です。
【減価償却できる・できない資産の例】
| 減価償却できる資産 | 減価償却できない資産 |
|---|---|
| 建物本体 | 土地 |
| キッチン設備 | 借入金の利息 |
| エアコン | 税金・保険料 |
このように、資産の種類によって減価償却の対象かどうかが異なるため、購入やリフォームの際は注意が必要です。
\買う前にチェックしないと損!/
インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!
法定耐用年数と減価償却 賃貸マンションやアパートの基礎知識
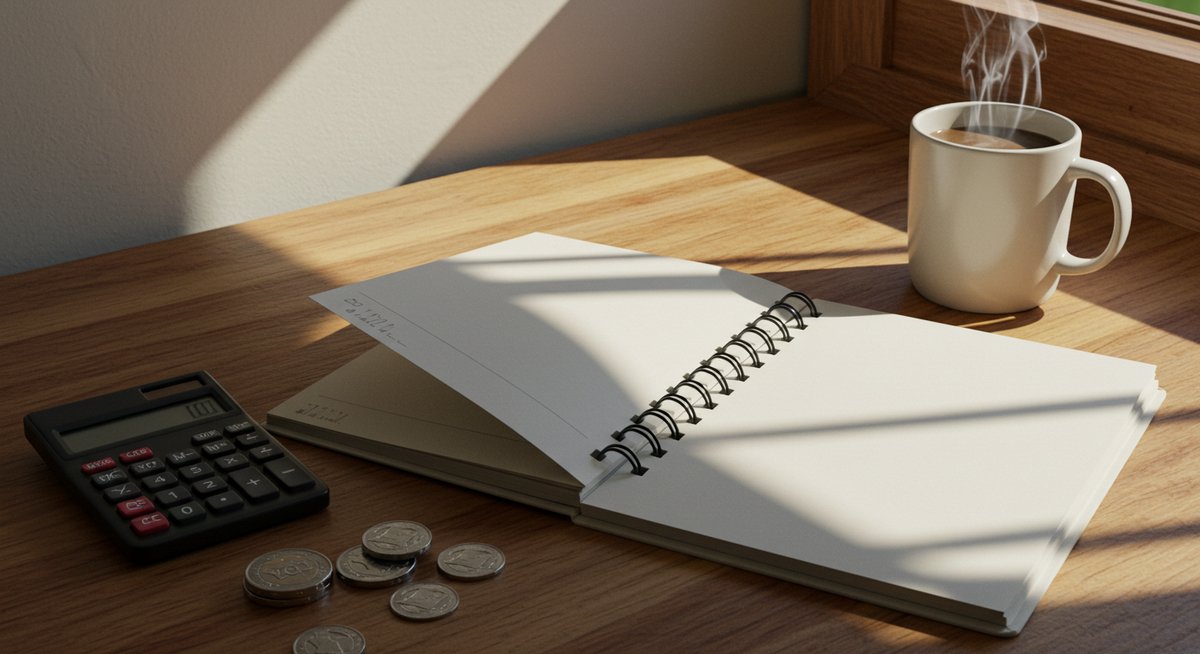
減価償却の計算には「法定耐用年数」が不可欠です。ここでは、建物の種類や構造ごとに異なる耐用年数や考え方、リフォーム部分への適用について解説します。
建物構造ごとの法定耐用年数の違い
法定耐用年数とは、国が定める資産ごとの使用可能期間の目安です。建物の構造によって耐用年数が異なり、減価償却の計算にも影響します。
例えば、主な賃貸物件の例は次の通りです。
| 構造の種類 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 22年 |
| 鉄骨造 | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |
この年数を基に減価償却期間が決まるため、購入前に構造ごとの違いをしっかり把握しておくことが大切です。
中古マンションやアパートの耐用年数の考え方
中古物件を購入した場合、法定耐用年数の残り年数や「簡便法」と呼ばれる計算方法が用いられます。残耐用年数は、既存の耐用年数から築年数を差し引き、「その残り期間」で減価償却を行います。
また、築年数が法定耐用年数を超えている場合でも、一定の計算方法によって新たな耐用年数が設定されます。これにより、中古物件の減価償却期間が短くなるため、毎年の減価償却費が大きくなる傾向があります。購入前に必ず確認しましょう。
付属設備やリフォーム部分の耐用年数
建物本体とは別に、エアコンや給湯器、キッチンなどの設備部分は独自の耐用年数が定められています。また、リフォームで新しく設置・交換した設備も、その設備ごとの耐用年数で減価償却が可能です。
【主な付属設備の耐用年数】
| 設備・工事内容 | 耐用年数 |
|---|---|
| エアコン | 6年 |
| 給湯器 | 6年 |
| キッチン | 15年 |
リフォーム時には、どの工事が減価償却の対象となるかを確認し、正しい耐用年数で処理することが大切です。
耐用年数超過物件のリスクと対策
耐用年数を超えた物件は、減価償却ができなくなるため、経費として計上できる額が減る特徴があります。その結果、課税所得が増え、税負担が重くなる可能性があります。
このような場合、リフォームによる資産価値の向上や新たな物件の購入による減価償却資産の追加など、資産運用の見直しが求められます。長期的な経営計画を立て、リスクと対策を検討しましょう。
新築か中古+リノベかで迷っていたらぜひ読んでみよう!
何から始めたらいいかが分かる一冊です。
賃貸マンションやアパートの減価償却費 計算方法とシミュレーション
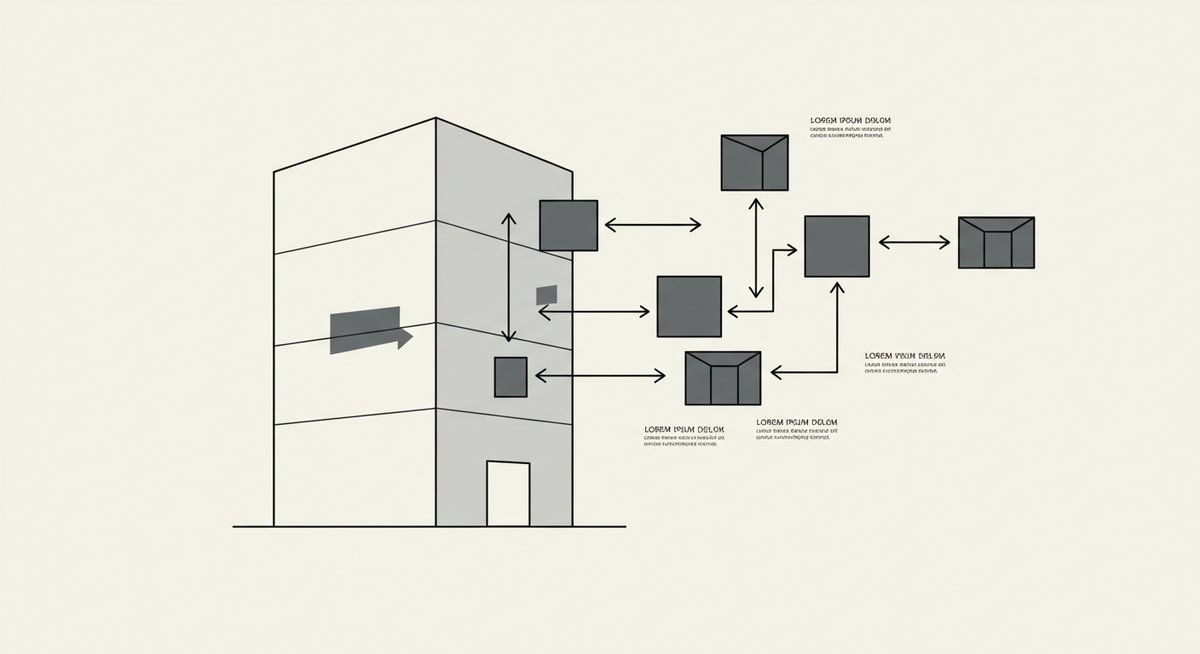
減価償却費の計算は賃貸経営の基礎です。ここでは、必要な項目や計算手順、新築と中古の違い、実際のシミュレーション事例も解説します。
減価償却費の計算に必要な項目と準備
減価償却費を計算するには、以下の項目が必要です。
- 建物や設備の取得金額(購入価格や工事費用など)
- 建物と土地の価格の内訳
- 法定耐用年数
- 取得年月日
これらの情報を整理しておくことで、スムーズに減価償却費を計算できます。購入時の契約書や領収書を必ず保管し、必要に応じて税理士や専門家に相談しましょう。
新築物件と中古物件の計算の違い
新築物件の場合、法定耐用年数をそのまま用いて計算します。一方、中古物件は、築年数によって減価償却期間が短縮されるため、1年あたりの減価償却費が大きくなります。
また、中古物件では「残存耐用年数」や「簡便法」と呼ばれる計算が必要となるため、取得時には必ず確認しましょう。必要に応じて税務署や専門家に相談するのが安心です。
建物本体と付属設備を分けた減価償却のメリット
建物本体と付属設備を分けて減価償却することで、それぞれの耐用年数に合わせて経費を計上できます。たとえば、エアコンや給湯器など短い耐用年数の設備は早く経費化できるため、節税効果が高まります。
また、将来的な設備交換やリフォームを計画的に進めやすくなり、キャッシュフローの管理にも役立ちます。分けて計算することは、賃貸経営の効率化にもつながるポイントです。
減価償却費のシミュレーション事例
具体的な金額でイメージしやすくするため、シミュレーション例を紹介します。
【シミュレーション例】
| 項目 | 新築RCマンション | 中古木造アパート |
|---|---|---|
| 取得金額 | 5,000万円 | 2,000万円 |
| 法定耐用年数 | 47年 | 22年(残10年) |
| 年間減価償却費 | 約106万円 | 約200万円 |
このように、中古物件は耐用年数が短くなる分、毎年の減価償却費が大きくなります。購入前に必ずシミュレーションを行い、収支計画を立てることが大切です。
投資家100人の話で学べる!
不動産投資の初心者にもおすすめの一冊。
減価償却が終わった後の賃貸物件オーナーの選択肢

減価償却期間が終了すると、税金や資産運用の状況が大きく変わります。ここでは、減価償却終了後のオーナーの選択肢や対策について解説します。
減価償却終了後の税負担とキャッシュフローの変化
減価償却が終わると、経費として計上できる金額が減るため、課税所得が増える傾向があります。そのため、税金の負担が重くなり、手元に残る現金(キャッシュフロー)にも影響が出ます。
特に長期保有の場合、減価償却終了後の税金対策や資金計画の見直しが必要です。早めに家計のシミュレーションを行い、将来の備えを検討しましょう。
売却 更地化 建て替えの検討ポイント
減価償却が終了した物件については、売却や更地化、建て替えといった選択肢も出てきます。
- 売却:資産を現金化できるが、譲渡所得税などの課税が発生する場合もある
- 更地化:再開発や新たな活用が可能になる
- 建て替え:新しい建物を建てることで再び減価償却が可能
それぞれの選択肢にはメリット・デメリットがあるため、将来的なニーズや資産価値を考えながら判断しましょう。
減価償却終了前にできる節税や資産活用策
減価償却が終わる前にリフォームや設備更新を行い、新たな減価償却資産を増やすことで、経費計上の余地を広げることが可能です。
また、物件ごとの資産価値や周辺環境を見直し、今後の運用方針を立てておくことも重要です。早めの準備で、節税や資産活用の選択肢が広がります。
法人化や新たな物件購入でのリスク分散
個人での賃貸経営にリスクや税負担が大きくなった場合は、法人化によって税率や経費処理の柔軟性を高める方法もあります。また、新たな物件を購入して減価償却の対象資産を増やすことで、経営リスクを分散することも可能です。
ただし、法人化や追加購入には手間やコストがかかります。専門家に相談し、自身に合ったリスク分散策を選択しましょう。
賃貸物件のリフォームや修繕と減価償却の関係
リフォームや修繕を行った際、その費用が減価償却できるかは経営に大きく影響します。税制上の扱いや注意点をまとめました。
リフォーム費用は減価償却の対象になるか
リフォーム費用のうち、建物の価値を大きく高めるような工事(例:増築や大規模改修)は「資本的支出」として減価償却の対象になります。一方、日常的な修繕や小規模な改装は「修繕費」として一括経費計上が認められる場合もあります。
どちらに該当するかは工事の内容や規模によって判断されるため、見積もりや工事内容は詳細に記録しておくことが大切です。
修繕費と資本的支出の違いと税務上の扱い
修繕費とは、建物や設備の現状維持や原状回復を目的とした支出を指し、その年の経費として一括で計上できます。資本的支出は、建物の価値や耐用年数を高める大規模な工事費用で、減価償却によって数年に分けて経費計上されます。
【違いの比較表】
| 項目 | 修繕費 | 資本的支出 |
|---|---|---|
| 経費計上時期 | 一括 | 複数年分割 |
| 例 | 壁紙張替え | 増築・キッチン交換 |
判断が難しい場合は、税務署や専門家に確認するのが安心です。
費用計上や減価償却方法の注意点
リフォームや修繕の費用が大きい場合、すべてを一括経費にできるとは限りません。内容によっては分割計上が求められるため、見積書や工事写真を整理し、支出の内容が判断できるようにしておきましょう。
記帳ミスや計上漏れは税務調査で指摘されやすいポイントです。毎年の確定申告前に、必ず領収書や書類を見直しておくことをおすすめします。
原状回復や設備交換時の減価償却のポイント
賃貸物件の退去時に行う原状回復や、設備の交換工事も、内容によって減価償却の対象となる場合があります。たとえば、エアコンや給湯器の交換は設備ごとの耐用年数に基づき減価償却が可能です。
原状回復工事のうち、壁紙張替えやクリーニングなどは修繕費として一括経費になることが多いですが、工事内容が資本的支出にあたる場合は分割計上が必要です。工事内容ごとに分類し、適切に経費処理を行いましょう。
賃貸経営で減価償却を賢く活用するための実践アドバイス
減価償却を活用するためには、正しい申告や専門家との連携が重要です。ここでは実践的なアドバイスや注意点をまとめます。
確定申告時の減価償却費計上のコツ
減価償却費は毎年の確定申告で忘れずに計上することが大切です。計算ミスや記入漏れを防ぐため、事前に必要書類を整理し、減価償却資産ごとに一覧にまとめておくと便利です。
- 建物、設備ごとに取得価額・耐用年数・残額を管理
- 領収書や見積書の保管
- 分かりやすい管理台帳の作成
これらを徹底することで、申告ミスや記帳漏れを防ぎ、スムーズに手続きを進められます。
節税効果を最大化するための申告方法
減価償却は、適正な金額を計上することで節税効果を最大限に引き出せます。設備ごとに分けて計上し、短い耐用年数のものは早めに経費化するのがポイントです。
また、大規模リフォームや設備更新のタイミングを見計らい、複数年に分けて計上することで、所得の変動をなだらかにできる場合もあります。計画的な申告が節税のコツです。
減価償却を相談できる専門家や建築会社の選び方
減価償却や税務処理は複雑なため、信頼できる税理士や経験豊富な建築会社と連携することが大切です。
- 賃貸物件の経理経験が豊富な税理士を選ぶ
- 減価償却やリフォーム計画に詳しい建築会社に相談
- 実績や口コミで信頼性を確認
専門家のサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して経営を行うことができます。
よくある質問と注意すべきトラブル事例
実際の賃貸経営では、減価償却に関する疑問やトラブルも多く聞かれます。たとえば、「土地も減価償却できるのか」「リフォーム費用はすべて経費になるのか」などです。
また、減価償却費の計上ミスや、修繕費と資本的支出の分類違いもトラブルの原因になります。申告内容に不安がある場合は、必ず専門家に確認し、誤った処理を避けましょう。
まとめ:賃貸物件オーナーが減価償却で押さえるべき重要ポイント
減価償却は賃貸物件オーナーにとって、税金対策や資産管理の要となる仕組みです。法定耐用年数や資産ごとの差、リフォームや修繕費の扱いまで、基礎をしっかり理解することが経営の安定につながります。
今後も定期的に情報を見直し、必要に応じて専門家の意見も取り入れながら、賢く減価償却を活用していきましょう。
\買う前にチェックしないと損!/
インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!











