賃貸物件を探すとき、多忙や遠方からの引越し、人気物件の争奪戦などの事情で「内見せずに契約する」か迷う方は少なくありません。実際に契約したあとに「こんなはずではなかった」と後悔したくないけれど、現地に行けない・すぐに決断しなければ埋まってしまう、といった悩みもよく耳にします。
この記事では、内見しないで賃貸契約をする人の割合や、その背景、メリット・リスク、後悔しないための工夫まで幅広く解説します。これからお部屋探しを考えている方が納得して物件を選ぶためのヒントとして、ぜひご活用ください。
内見しないで契約する人の割合と近年の傾向
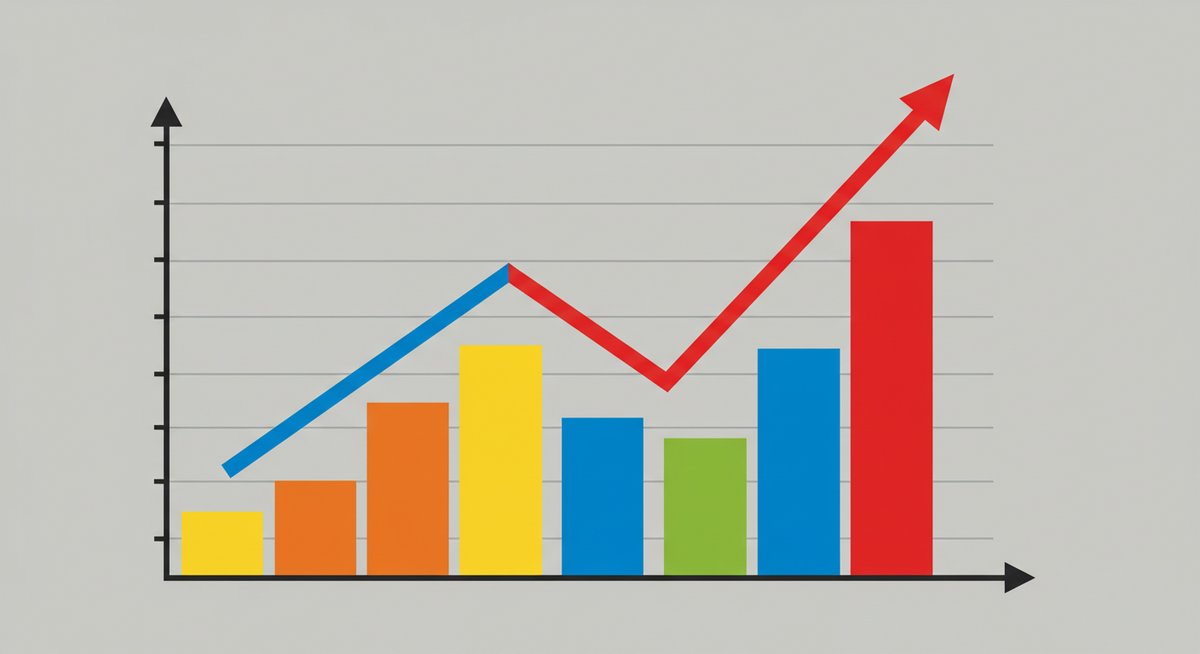
最近では、賃貸物件の契約手続きがオンラインで進むことが増え、実際に現地を訪れずに契約を決める方も目立つようになっています。特にコロナ禍以降、非対面の暮らし方や働き方が広がったことも影響しています。
遠方からの転居や急な引越し、人気物件の早期申し込みなど、さまざまな事情で「内見なし契約」を選ぶ人が増えているという声も多く聞かれます。
最新の調査データから見る内見せずに契約した人の割合
近年の調査によると、賃貸物件を内見せずに契約した人の割合は、全体の10~20%程度となっています。以前はほとんどが現地を訪れてから契約していましたが、オンラインサービスの発展やコロナ禍の影響で、内見せずに契約するケースが急増しています。
特に、2020年以降は「内見なし契約」の割合が顕著に増えており、物件検索サイトや不動産会社の独自集計でもこの傾向が明らかになっています。内見なしで契約した方の満足度は分かれるものの、利便性を重視する層からは一定の支持を受けているようです。
年代やエリアによる内見なし契約の傾向の違い
内見せずに契約する傾向は、年代や住むエリアによっても違いがあります。特に20~30代の若い世代は、インターネットで情報を収集し、写真や動画をもとに意思決定することに抵抗が少ないため、内見なしで契約する割合が高い傾向にあります。
一方、地方よりも都市部や首都圏のほうが内見なし契約が増えています。理由としては、人気物件の競争が激しく、スピード感が求められるためです。地方ではまだ現地をしっかり確認してから契約する人が多い傾向が見られます。
内見しないで契約が増加している背景
内見なし契約が増えている背景には、社会のデジタル化やライフスタイルの変化が関係しています。スマートフォンやパソコンから膨大な物件情報にアクセスできるようになり、写真や動画、間取り図などを見て判断する人が増えました。
また、コロナ禍で対面のやり取りを避けたい人が増えたことも大きな要因です。オンラインでの相談や契約、VR内見といった新しいサービスが充実したことで、現地を訪れなくても比較的安心して契約できる環境が整いつつあります。
内見しないで契約する人が多い時期とその理由
内見なし契約が多くなるのは、特に引越しシーズンである1月から3月です。この時期は転勤や入学などで物件探しが集中し、良い部屋はすぐに埋まってしまうため、内見の時間を待てない方が増える傾向があります。
また、急な転勤や進学、住み替えなどで「とにかく早く部屋を決めなければならない」という事情がある場合、現地確認を省略する人が多くなります。物件の供給よりも需要が上回る繁忙期に、内見なし契約が増えやすいのが特徴です。
新築か中古+リノベかで迷っていたらぜひ読んでみよう!
何から始めたらいいかが分かる一冊です。
内見しないで契約する理由とメリット

内見せずに契約する背景には、それぞれの事情や明確なメリットがあります。情報収集やIT技術の進化によって、以前よりも内見なしで決断しやすい環境が広がっています。
ここでは、主な理由と内見なし契約の利点について具体的にご紹介します。
物件を早く押さえたいという先行申込のニーズ
特に人気の高い物件は、内見予約をしているうちに別の人に申し込まれてしまうことがあります。スピードが求められる状況では、現地確認よりも契約の優先順位を上げる人が増えています。
このような場合、まだ写真や資料だけで判断し、内見せずに契約してしまうことで、他の希望者よりも早く物件を押さえることができます。とくに都市部の駅近物件や新築物件などは、この「先行申込」の動きが活発です。
遠方からの引越しで内見が難しい場合
遠方からの転勤や進学、結婚などで引越し先を探す場合、内見のためだけに何度も現地を訪れることは大きな負担になります。交通費や滞在費もかかり、仕事や学校の都合で日程調整が難しいことも多いです。
このような事情があると、写真や動画、詳細な資料をもとに現地を見ずに契約するケースが増えています。最近では、初めての土地に引っ越す人向けに、「遠隔地契約」に慣れた不動産会社がサポート体制を整えていることも、内見なし契約を後押ししています。
物件が未完成または入居者が退去前の場合
新築物件やリフォーム中の物件、前の入居者がまだ退去していない場合は、現地内見ができないケースもあります。とくに新築マンションやアパートでは、完成前の段階で申込みを受け付けることが一般的です。
この場合、図面や完成イメージ、同じ間取りの別部屋の写真などで判断する必要があります。入居希望者が多い物件では、完成前から申込が殺到するため、内見しないで契約することが珍しくありません。
VR内見やオンライン内見の普及による選択肢の拡大
近年は、360度カメラを使ったVR(バーチャルリアリティ)内見や、リアルタイムで担当者が部屋を案内するオンライン内見サービスが普及しています。スマートフォンやパソコンから、実際にその場にいるような感覚で内装や景色を確認できるのが特徴です。
これにより、遠方に住んでいても移動せずに細かい部分までチェックすることが可能になりました。表や写真、動画だけでなく、臨場感のある映像を活用することで、内見なしでも納得して契約できる選択肢が増えています。
内見しないで契約するリスクと後悔しやすいポイント

内見せずに契約することには、メリットだけでなくリスクも伴います。現地を直接確認しないことで、予想外のトラブルや後悔につながることもあるので注意が必要です。
ここでは、内見しない場合によくあるリスクや、気をつけたいポイントを解説します。
図面と実際の間取りや広さが異なるリスク
間取り図や写真だけでは、実際の部屋の広さや使い勝手を正確に把握できないことがあります。図面上は広く見えても、家具を置いたときのイメージや天井の高さ、収納の奥行きなどにギャップが生じる場合があります。
結果として「手持ちの家具が入らなかった」「思ったより狭かった」と感じることが多いです。部屋の細かい寸法や、出っ張り・梁(はり)など見落としやすい部分まで注意して確認する必要があります。
写真やデータだけでは分からない設備や室内の状態
写真や資料に写っている部分以外に、見落としやすい設備の不具合や、壁紙の汚れ、水回りの劣化などがあるケースも珍しくありません。とくに古い物件やリフォーム物件では、写真が過去の状態のまま掲載されていることもあります。
現地確認を省略すると、実際に入居してから「想像と違った」「設備が思ったより古かった」と後悔する原因にもなります。細部まで確認できる写真や動画を不動産会社に依頼することが大切です。
騒音や治安など周辺環境がイメージと違うケース
周辺環境は物件の資料や写真からは分かりにくい部分です。たとえば、近隣の騒音、交通量、治安、夜の雰囲気などは、実際に現地を歩かないと把握が難しいです。
入居後に「思ったよりうるさかった」「周辺の雰囲気が合わなかった」と感じる方もいます。周辺環境に関する情報も事前に調べたり、地図サービスや口コミを活用したりして補うことが重要です。
契約後にキャンセルできないことによるトラブル
賃貸契約は、申し込み後や契約書類の締結後は原則としてキャンセルできない場合が多いです。内見せずに契約した結果、後から気になる点が見つかっても、「やっぱりやめたい」と思っても違約金が発生したり、費用が戻らないケースがあります。
トラブルを防ぐためにも、契約内容やキャンセル時のルールを事前にしっかり確認しておくことが大切です。納得できるまで不明点を質問し、不動産会社から十分な説明を受けるようにしましょう。
内見なしで賃貸契約する際の注意点と対策

内見せずに契約する場合は、リスクをできるだけ減らすために情報収集や確認作業を徹底することが重要です。不安を残さないよう、次のような点に注意しておきましょう。
不動産会社に追加の写真や資料を依頼する
現地を訪れられない場合は、不動産会社に対して「水回り」「収納」「ベランダ」「壁や床の状態」など、気になる部分の追加写真を必ず依頼してください。できるだけ多くの角度から撮影した写真や、備品・設備の動作状況も確認できると安心です。
また、間取り図だけでは分かりにくい部分や、気になる点があれば遠慮せずに質問しましょう。不動産会社にしっかり要望を伝えることが、後悔を減らすポイントです。
Googleマップやハザードマップで周辺環境を確認
現地に行けない場合でも、Googleマップで物件周辺の様子や、最寄り駅からのルート、周辺施設の位置関係などを簡単に調べることができます。ストリートビューを使えば、実際の街並みや建物の外観も確認しやすいです。
さらに、自治体が公開しているハザードマップで「洪水」「土砂災害」「浸水リスク」などの有無も事前にチェックしておくと安心です。立地の安全性や利便性も事前に調べておきましょう。
オンライン内見やVR内見を活用する方法
最近は、ビデオ通話を利用したオンライン内見や、VR内見サービスを提供する不動産会社が増えています。これらを利用することで、現地に行かずに室内や設備を詳細に確認できます。
担当者にカメラを動かしてもらい、気になる部分をアップで見せてもらうなど、対面の内見に近い感覚でチェックできます。気になる方は、事前にどのような内見サービスが利用できるか不動産会社に相談してみましょう。
先行契約や申込時に確認すべきポイント
内見せずに「先行契約」や「先行申込」を行う場合は、キャンセル規定や申込金の返金条件、設備の状況などを必ず確認しましょう。後からトラブルにならないよう、契約前に内容をよく読み、不明点は書面で確認しておくことが大切です。
また、賃貸借契約書や重要事項説明書の内容もしっかり事前にチェックし、納得できない部分があれば修正や説明を求めるようにしましょう。焦らず慎重に進めることが安心につながります。
内見できない場合のおすすめ対処法
どうしても内見が難しい場合でも、できるだけ現地の状況や入居後の生活をイメージできる工夫を取り入れましょう。代替手段を上手に活用することで、失敗や後悔を防ぎやすくなります。
同じ建物の別の部屋を内見する選択肢
希望する部屋が内見不可でも、同じ建物に空き部屋があればそちらを見学することも可能です。間取りや設備が類似していれば、実際の広さや日当たり、共用部分の雰囲気などを体感できます。
ただし、階数や部屋の位置が違うと状況が異なることもあるため、違いについて不動産会社に詳しく説明してもらうと安心です。
前入居者の立会いや口コミ情報の活用
前の入居者が知人であれば、リアルな住み心地や周辺環境について直接話を聞くのも有効です。また、インターネット上の口コミやレビューサイト、SNSで実際の入居者の体験談を参考にするのもおすすめです。
口コミを利用する場合は、下記のようなポイントを参考にしましょう。
- 騒音や住民の雰囲気
- 設備の使い勝手や不具合
- 日当たりや湿気、周辺の治安
物件資料の詳細なチェックポイント
現地に行けない分、物件資料や契約書を細かくチェックすることが大切です。たとえば、以下のような点を見落とさないようにしましょう。
| チェック項目 | 確認ポイント |
|———————|———————-|
| 設備一覧 | 備品の新しさ・故障有無 |
| 間取り図 | 家具の配置や動線 |
| 重要事項説明書 | 特約や禁止事項 |
疑問点や不安なことがあれば、必ず不動産会社に質問し、納得できるまで情報を集めておくことが重要です。
契約前に不明点をしっかり相談する
内見できない不安がある場合は、とにかく事前の相談を徹底しましょう。契約内容や設備、周辺環境、住人のマナーなど、気になることは全てリストアップして質問し、不動産会社から説明や追加資料をもらいましょう。
また、メールや書面でやりとりを残しておくと、後からのトラブル防止にも役立ちます。納得できるまでやり取りを重ねることで、安心して契約できる可能性が高まります。
まとめ:内見しないで契約する割合と後悔しない賃貸選びのポイント
最近では、賃貸物件を内見せずに契約する人が増えていますが、満足度の高い部屋選びには工夫が必要です。内見しない契約には、スピーディーに物件を決められるというメリットがある一方、現地を確認しないことによるリスクも存在します。
後悔しないためには、写真や動画などの情報を十分に集め、不安な点は必ず不動産会社に確認しましょう。オンライン内見やVR内見、口コミや地図サービスなどを上手に活用することも大切です。また、契約書の内容やキャンセル規定をきちんと理解し、納得できるまで相談することで、安心して新しい住まいを選ぶことができます。
納得のいく物件探しのために、一つ一つの手続きを丁寧に進めることをおすすめします。
投資家100人の話で学べる!
不動産投資の初心者にもおすすめの一冊。











