賃貸審査で年収が足りないとどうなるか知っておきたいポイント
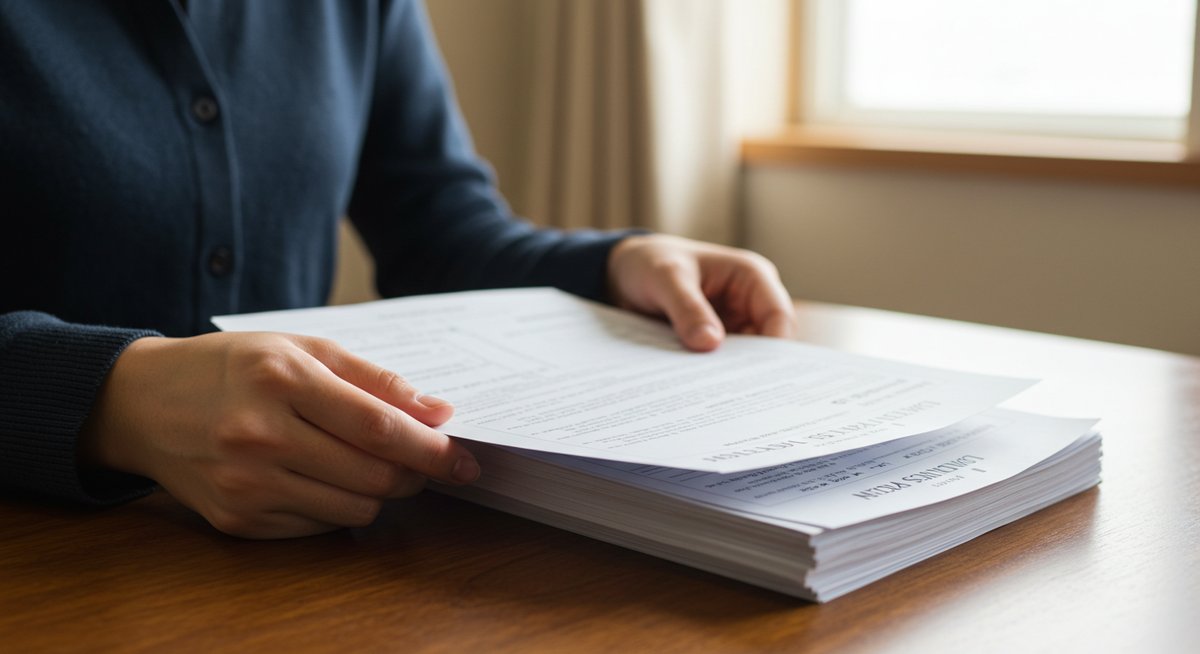
賃貸物件を借りる際、年収が審査基準に満たない場合が気になる方は多いです。ここでは、年収と審査の関係について分かりやすく解説します。
家賃と年収のバランスが重視される理由
賃貸審査では、家賃と借りる人の年収のバランスが特に重視されます。なぜなら、家賃が収入に対して高すぎると、支払いが滞るリスクが高まると見なされるためです。一般的には「家賃は手取り月収の3分の1程度までが望ましい」とされています。これは生活費や貯金、他の支出も無理なくこなせる範囲であると考えられているからです。
たとえば、手取り月収15万円の場合、家賃は5万円程度が目安となります。もしこれを大幅に超える家賃の物件を希望すると、「支払いが続かないのでは?」と不動産会社やオーナーから判断されやすくなります。生活全体の安定性を重視し、家賃と年収のバランスを見極めることが大切です。
年収が基準に満たない場合に審査で見られる点
年収が物件の基準に届かない場合でも、すぐに審査が通らなくなるわけではありません。不動産会社やオーナーは、他の収入源や貯蓄、職歴の安定性なども総合的に確認します。これにより、年収が基準より少し足りなくても、信頼できると判断されれば審査に通る可能性があります。
また、過去の家賃支払い履歴や、転職歴の多さもチェックされる場合があります。こうしたポイントは、「毎月しっかりと家賃を払えるかどうか」を見極めるためです。年収だけでなく、生活全体の安定感をアピールできると有利です。
年収以外で重視されるポイント
審査では年収以外にもさまざまな項目が重視されます。たとえば、職業の安定度や雇用形態、貯蓄額、過去の信用情報などです。特に正社員や公務員のような安定した職業の場合、年収が少し基準に満たなくてもプラスに評価されることがあります。
また、家賃の支払いを補うための保証人や保証会社の利用も重要です。保証人がしっかりしていれば、万が一の際にも家賃滞納リスクが減ると判断されます。職業や貯金、保証人の有無なども、年収と同じくらい重視されるポイントです。
\買う前にチェックしないと損!/
インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!
賃貸審査に落ちやすい人の特徴と注意点

賃貸審査では、年収だけでなく生活や収入の安定性も問われます。ここでは、審査に通りにくい人の特徴や気を付けたい点をまとめます。
収入や雇用形態が不安定な場合の影響
アルバイトや短期派遣など、雇用形態が安定していない場合は、審査時に不利になることが多いです。これは、収入が急に減る可能性や、職を失うリスクが高いと判断されるためです。特に、雇用期間が短かったり、勤続年数が1年未満の場合は注意が必要です。
また、非正規雇用やフリーランスといった働き方も、安定した支払いが見込めるかどうかがポイントとなります。収入の変動が大きい方は、収入証明書や貯金残高の提出が求められる場合もあります。雇用形態が不安定な場合は、他のポイントで信頼性をアピールする必要があります。
借金や家賃滞納の履歴があるときのリスク
過去に家賃の滞納があったり、消費者金融などでの借金が多い場合は、審査で大きなマイナス要因になります。家賃の支払い遅れの履歴や、信用情報に事故履歴があると、「今後も同じトラブルが起きるかもしれない」と警戒されます。
クレジットカードの返済遅れや、現在の借金残高も確認されることがあります。こうした事情がある場合は、事前に整理し、支払い能力を示す資料を用意しておくことが大切です。信用情報は簡単に回復できないため、日ごろから丁寧な管理を心がけたいところです。
連帯保証人や緊急連絡先の重要性
連帯保証人は、借主が家賃を払えない場合に代わりに支払う責任を持つ人です。保証人がいない場合や、緊急連絡先が曖昧だと、審査で不利になることがあります。とくに、安定した収入や持ち家がある保証人は信頼度が高いです。
もし保証人を立てられない場合は、保証会社の利用が一般的ですが、保証会社も審査を行います。また、緊急連絡先として家族や勤務先の情報をしっかり記載することも重要です。保証人や連絡先によって審査の印象が大きく変わるため、事前に相談しておくと安心です。
新築か中古+リノベかで迷っていたらぜひ読んでみよう!
何から始めたらいいかが分かる一冊です。
年収が足りない場合でも賃貸審査を通過する方法

年収が基準に満たない場合でも、工夫次第で賃貸審査を通過できる場合があります。ここでは、具体的な方法を紹介します。
家賃の安い物件や条件緩和の住居を選ぶコツ
まず、家賃が安めの物件を選ぶことで審査に通りやすくなります。築年数が経過している物件や、駅から少し離れている住居は、家賃が低めに設定されていることが多いです。
また、「敷金・礼金ゼロ」や「保証人不要」といった条件緩和の物件も選択肢に入ります。これらの物件は、オーナーが入居者を早く決めたいと考えている場合が多く、審査基準がやや緩やかな傾向があります。以下のようなポイントを意識すると良いでしょう。
- 家賃が手取り月収の1/3以下
- 築年数が古い物件
- 駅から徒歩15分以上の場所
- 敷金・礼金ゼロの物件
自分の収入に合った物件選びが、審査突破の第一歩となります。
預金残高や副業収入など他の資産でアピールする方法
年収が足りない場合でも、預金残高や副業収入など、他の資産をアピールすることで審査が通りやすくなることがあります。たとえば、通帳のコピーや副業の収入明細などを提出し、一定の貯蓄や収入があることを証明します。
特に、まとまった金額の預金がある場合や、安定した副業収入が毎月ある場合は、その証明を積極的に提出しましょう。不動産会社も「万が一収入が減っても、家賃支払いに余裕がある」と判断しやすくなります。定期的な入金記録や、給与明細をまとめておくことがポイントです。
親族や会社名義で契約する選択肢
もし自分の年収や条件だけでは審査が厳しい場合、親族や勤務先の会社名義で契約する方法もあります。親や兄弟など収入がしっかりしている家族が契約者となることで、審査が通りやすくなる場合があります。
また、会社の転勤や単身赴任などで、企業が借り上げ社宅として契約するケースも増えています。この場合、会社の信用力が審査の基準となるため、個人の年収が足りない場合でもスムーズに契約できることがあります。どちらの場合も、事前に契約条件や名義、責任範囲をしっかり確認することが大切です。
投資家100人の話で学べる!
不動産投資の初心者にもおすすめの一冊。
審査を有利に進めるための事前準備と対策

賃貸審査を有利に進めるには、事前の準備が重要です。必要な書類や情報をそろえることで、信頼度を高めることができます。
必要書類の準備と正しい記入方法
賃貸審査では、申込書や身分証明書、収入を証明する書類などが必要です。申込書の記入は正確・丁寧に行い、記入漏れや誤字脱字がないよう注意しましょう。
具体的には、以下のような書類が一般的に必要とされます。
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 収入証明書(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)
- 在職証明書や健康保険証
- 住民票
書類が揃っていない場合や、記入ミスがあると審査が遅れることもあるため、事前にチェックリストを作成しておくと安心です。
不動産会社や保証会社への相談でできること
年収や条件に不安がある場合は、物件を探す段階で不動産会社や保証会社に相談するのも有効です。希望条件や不安な点を伝えることで、審査基準が比較的緩やかな物件を紹介してもらえることがあります。
また、保証会社の審査を先に受けておき、自分の条件でどの程度まで通るかを確認する方法もあります。不動産会社と信頼関係を築くことで、追加書類や説明が必要な場合も柔軟に対応してもらえるため、積極的に相談してみましょう。
クレジットや公共料金の支払い履歴を整える
審査では、信用情報も参考にされることがあります。クレジットカードや携帯電話、公共料金の支払いを遅らせず、きちんと管理することが大切です。
たとえば、過去に支払いが遅れたことがある方は、現在の支払い状況を整えてから申し込むことをおすすめします。また、引き落とし口座の残高に余裕を持たせる、請求書の管理を徹底するなど、日常の小さな習慣が信用につながります。信用情報の積み重ねが、賃貸審査を通過するための大切なポイントとなります。
まとめ:賃貸審査で年収が足りない場合の対策と成功のポイント
賃貸審査で年収が基準に満たない場合でも、他の資産や保証人によるアピール、条件に合った物件選びなど、さまざまな方法で審査を突破できる可能性があります。事前の準備や相談も重要なポイントです。
年収に自信がない場合は、まず家賃と収入のバランスを見直し、自分の条件に合う物件を探しましょう。必要書類の準備や、日常の信用管理を徹底することも審査成功の鍵となります。自分に合った方法で、安心して新生活をスタートできるよう工夫してみてください。
\買う前にチェックしないと損!/
インテリア・寝具・収納の今だけ数量限定クーポンで快適な生活に!











