住まいをより快適に保つためにリフォームを検討する方が増えていますが、費用の捻出は大きな悩みの一つです。親や家族からリフォーム資金の援助を受ける際、税金がかかるのか、どのような手続きが必要なのかが気になる方も多いのではないでしょうか。リフォーム資金の贈与には贈与税が関わる場合があるため、事前に基本的な知識を知っておくことが安心につながります。また、非課税となる特例制度や、手続きで注意したいポイントも理解しておきたいものです。本記事では、リフォーム資金贈与に関する非課税の仕組みや手続き、具体的な注意点についてわかりやすく解説します。大切な住まいのために、制度を正しく活用しましょう。
リフォーム資金の贈与と非課税制度の基本を知ろう

リフォームのために家族から資金を受け取る場合、贈与税がかかるかどうかが気になるところです。ここでは贈与税の基本や非課税となる制度について、まず押さえておきましょう。
リフォーム費用の贈与に贈与税が発生するケース
家族や親族からリフォーム費用としてお金をもらうと、その金額によっては贈与税がかかる場合があります。たとえば、親からまとまった資金を受け取る場合、単なる援助と考えがちですが「贈与」とみなされるため注意が必要です。
贈与税は、1年間に受け取った贈与額の合計が基準を超えると発生します。基準額や税率は受け取る人と贈与者との関係によって異なることもあります。特に、資金の使い道が住宅購入やリフォームであっても、贈与としてカウントされる点を意識しておきましょう。
また、親子間であっても事前に申告や手続きが必要になる場合があります。資金援助を受ける前に、どのような場合に贈与税が発生するのかを確認しておくと安心です。
年間110万円以内の贈与が非課税となる仕組み
リフォーム資金として贈与を受ける際、最も身近な非課税の仕組みが「年間110万円以内」の贈与です。これは1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以内なら、贈与税がかからないという制度です。
この仕組みは、贈与を受ける人ごとに適用されます。たとえば、親から100万円、祖父母から10万円を受け取った場合、その年の合計は110万円となり、贈与税は発生しません。
ただし、110万円を超える金額を受け取った場合は、その超えた部分に対して贈与税がかかります。まとまったリフォーム費用を受ける場合、数年に分けて贈与を受けるなど工夫することで、税金の負担を抑えることも検討できます。
住宅取得等資金贈与の特例とは
リフォーム資金の贈与には「住宅取得等資金の贈与税非課税の特例」という制度もあります。これは一定の条件を満たす住宅のリフォームや増改築に使う資金を、親や祖父母などから贈与された場合、一定額まで贈与税がかからない特別な制度です。
たとえば、省エネ改修やバリアフリー工事など、基準に適合したリフォームであれば、最大で数百万円から1,000万円を超える非課税枠が設けられることがあります。非課税となる金額や条件は年度によって変わるため、必ず最新の情報を確認しましょう。
この特例を使うことで、大規模なリフォームでも贈与税の負担を大きく軽減することが可能です。ただし、申告や必要書類の提出が求められるため、計画的に準備することが大切です。
新築か中古+リノベかで迷っていたらぜひ読んでみよう!
何から始めたらいいかが分かる一冊です。
非課税でリフォーム資金を受け取るための条件と手続き
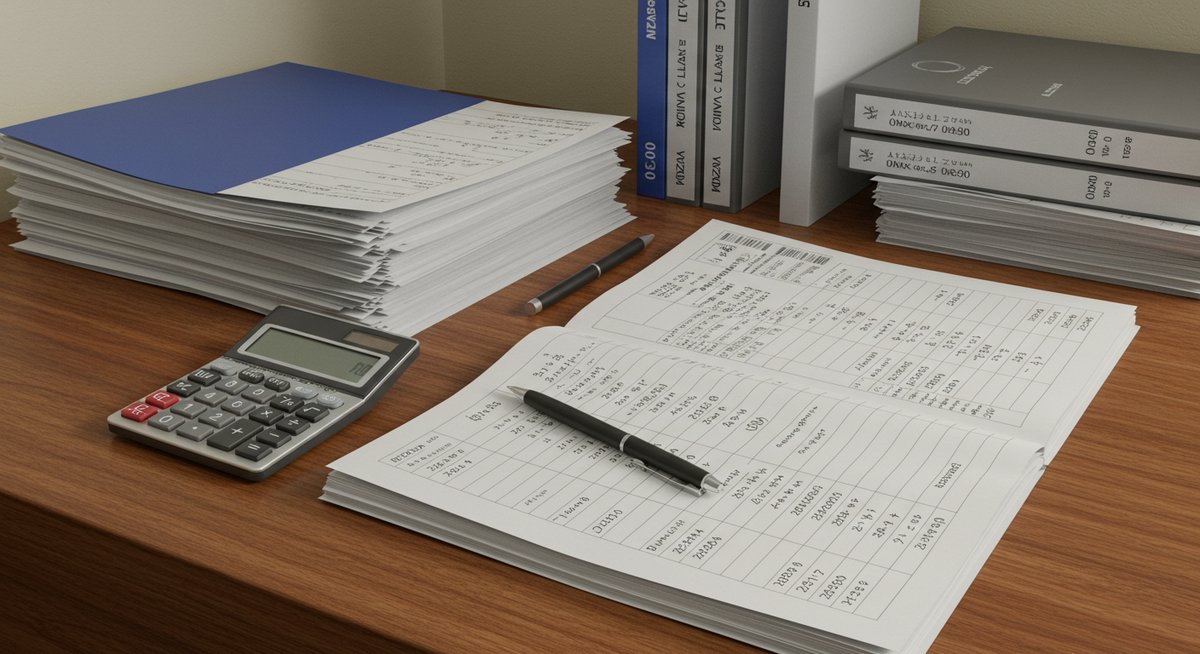
せっかくの非課税制度も、要件や手続きを知らずにいると活用できません。ここでは、非課税の条件や必要な手続きについて具体的に解説します。
非課税となるリフォーム工事の要件
住宅取得等資金贈与の非課税特例を利用するには、リフォーム内容が一定の要件を満たしている必要があります。たとえば、省エネ性能を高める工事や、耐震性の向上、バリアフリー化を目的としたリフォームが対象となる場合が多いです。
また、工事費用が一定額以上であることや、リフォーム後の住宅が自分や家族の居住用であることも条件となります。対象外となるのは、単なる壁紙の張替えや設備の部分交換など、日常的な修繕に該当する工事です。リフォームを計画する際は、非課税となる要件に該当するかどうかを事前に業者や税理士などに相談するのがおすすめです。
主な非課税対象リフォームの例は以下の通りです。
- 省エネ改修(断熱、窓の二重化など)
- 耐震補強工事
- バリアフリー工事(手すり設置、段差解消など)
非課税制度を利用するために必要な申告と書類
非課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の確定申告期間中に税務署で申告が必要です。申告の際には、リフォーム工事が非課税要件を満たしていることを証明するための書類が必要となります。
主な必要書類は以下の通りです。
- 贈与を受けたことを証明する書類(贈与契約書など)
- リフォーム工事の契約書や領収書
- 工事内容が要件を満たしていることを証明する書類(工事証明書など)
- リフォーム後の住宅の登記事項証明書
これらの書類が揃っていないと、非課税制度が適用されないことがあるため、リフォームの計画段階から書類の準備を進めておきましょう。工事完了後にまとめて書類を集めようとすると、証明書の取得に時間がかかることもあるので注意が必要です。
非課税枠を超えた場合の贈与税の計算方法
非課税枠を超えるリフォーム資金の贈与を受けた場合、その超過分に対して贈与税がかかります。贈与税は贈与金額から基礎控除額や各種非課税枠を差し引いた残りの金額に、税率をかけて計算されます。
贈与税の税率は累進課税となっており、贈与額が多いほど税率も高くなります。たとえば、父母から400万円のリフォーム資金を贈与され、非課税枠(仮に300万円とする)を100万円超えた場合、その100万円に課税されます。110万円の基礎控除が適用できる場合もあるため、実際の課税対象額はさらに減ることもあります。
贈与税の計算例を表にまとめました。
| 贈与額 | 非課税枠 | 課税対象額 |
|---|---|---|
| 400万円 | 300万円 | 100万円 |
毎年の税率や控除額は国税庁のホームページなどで最新情報を確認し、あらかじめ試算しておくと安心です。
ケース別リフォーム贈与の注意点とトラブル回避策

リフォーム資金の贈与は、家族の協力が大きな力になりますが、名義や申告漏れなど思わぬトラブルが起こることもあります。ケースごとの注意点を知ることで、安心してリフォームを進めましょう。
親から贈与された資金でリフォームする場合のポイント
親からリフォーム資金の援助を受ける場合、資金の流れを明確にしておくことが大切です。口頭でのやり取りだけで資金を受け取ると、後から課税対象とされたり、家計のトラブルにつながることがあります。
資金の贈与は、できるだけ贈与契約書を作成し、金融機関を通じて記録が残る形で行いましょう。また、贈与額が非課税枠を超えるなら必ず申告が必要です。贈与を受けた資金でリフォームをした証拠として、見積書や領収書は必ず保管してください。
親子間でもお金のやり取りは慎重に進めるのが安心です。制度を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
配偶者や親子で共有名義の住宅をリフォームする場合
配偶者や親子など複数人で共有している住宅をリフォームする場合、費用の負担割合や名義によって贈与とみなされる可能性があります。たとえば、夫婦共有名義のマンションをリフォームする際に、一方が全額を負担すると、その一部がもう一方への贈与と判断されることがあるためです。
この場合、リフォーム費用を出した人と、住宅の所有割合が一致するように調整することが一般的です。もし費用負担と名義が異なる場合は、専門家に相談し、適正な手続きを検討しましょう。
また、共有名義の物件では、リフォーム後の資産価値の変動や、将来の相続に関わる点も把握しておくと安心です。
実家のリフォーム費用を子どもが負担する際の注意点
実家のリフォームを子どもが費用を負担して行う場合、注意すべきポイントがあります。親の名義の住宅を子どもがお金を出してリフォームすると、逆に「子どもから親への贈与」と見なされる可能性があるためです。
この場合、贈与税の申告が必要になることがあるほか、資金の出所やリフォーム目的を明確にしておく必要があります。たとえば、将来の同居を見越して二世帯住宅にする場合などは、事前に税務署や専門家に相談しておきましょう。
また、リフォーム後に名義を変更する場合や、将来の遺産分割を見据えた話し合いも大切です。家族間の信頼関係を大切にしつつ、税務上のリスクも十分に理解しておきましょう。
リフォーム贈与とあわせて知っておきたい減税や他の特例

贈与税の非課税制度だけでなく、リフォームにはさまざまな減税や特例が用意されています。他の制度もあわせて知ることで、より賢くリフォーム資金を計画しましょう。
相続時精算課税制度の活用と注意点
リフォーム資金の贈与では、「相続時精算課税制度」を利用する方法もあります。これは、親や祖父母から一定額まで贈与税を支払わずに資金を受け取り、贈与者が亡くなった際の相続でまとめて精算される制度です。
この制度を利用すると、2,500万円までの資金を非課税で受け取ることができます。ただし、一度この制度を選択すると「その後の贈与もすべてこの制度で計算される」などのルールがあります。また、将来の相続時に税金の負担が生じるため、長期的な資金計画や相続対策とあわせて検討する必要があります。
利用の可否や手続きの詳細は複雑な部分もあるので、事前に税理士などに相談するのがおすすめです。
リフォームに使えるその他の減税制度
リフォームには、贈与税の非課税制度以外にもさまざまな減税制度が利用できます。たとえば、一定の省エネ改修やバリアフリーリフォームに対しては、所得税の控除や固定資産税の軽減措置が設けられていることがあります。
主なリフォーム減税制度の例は、以下の通りです。
- 住宅ローン控除(借入を利用したリフォームの場合)
- 省エネ改修工事による所得税控除
- バリアフリー改修工事による所得税控除・固定資産税の減額
それぞれの制度には、工事の内容や住宅の条件、申請に必要な手続きが細かく定められています。リフォームを計画する際は、該当する減税制度がないか事前に調べて、必要な申請や書類の準備を進めるとよいでしょう。
贈与税の申告漏れや未申告時のリスクと対応
リフォーム資金の贈与に関して申告が必要な場合、これを怠ると「申告漏れ」となり、追徴課税や延滞税が課されることがあります。特に、贈与税の非課税制度を利用するつもりだったのに、必要な申告や書類が不備だったことで制度が適用されなかったというケースも見られます。
申告漏れを防ぐには、贈与の事実や金額、資金の用途について証拠を残しておくことが重要です。贈与契約書や領収書、入出金の記録などをきちんと保管しておきましょう。もし申告を忘れてしまった場合でも、できるだけ早く税務署に相談して正しい手続きを取ることが、リスクを最小限に抑えるポイントです。
税制や手続きは毎年改正されることがあるため、最新情報の確認も欠かせません。
まとめ:リフォーム資金贈与の非課税制度を正しく活用して安心の住まいづくりを
リフォーム資金を家族から贈与された場合には、贈与税の発生や非課税制度の活用といったポイントを押さえておくことが大切です。年間110万円以内の贈与や住宅取得等資金の特例、相続時精算課税制度など、状況に合わせて最適な方法を選ぶことができます。
制度を利用するときは、非課税となるリフォームの要件や必要な手続き、申告方法などをしっかり確認して準備しましょう。特に家族間の資金援助は、申告漏れや名義トラブルを防ぐためにも、証拠書類をそろえ、計画的に進めることが大切です。
安心して理想の住まいを実現するためにも、税制や制度を正しく理解し、必要に応じて専門家のアドバイスを活用してください。
投資家100人の話で学べる!
不動産投資の初心者にもおすすめの一冊。











